 1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学 気候変動に伴う北極永久凍土の変化を示すモデル(Arctic Permafrost in climate change)
2025-01-17 マックス・プランク研究所地球温暖化により、北極圏の永久凍土が急速に融解し始めています。この地層は、現在の大気中の二倍の炭素を蓄えていますが、融解に伴い微生物が炭素を分解し、二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスを放出する...
 1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学 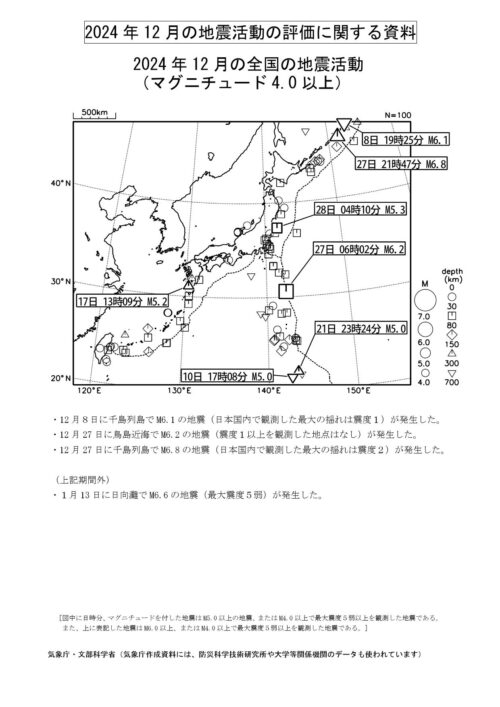 1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学 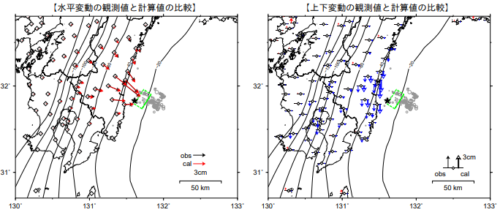 1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学 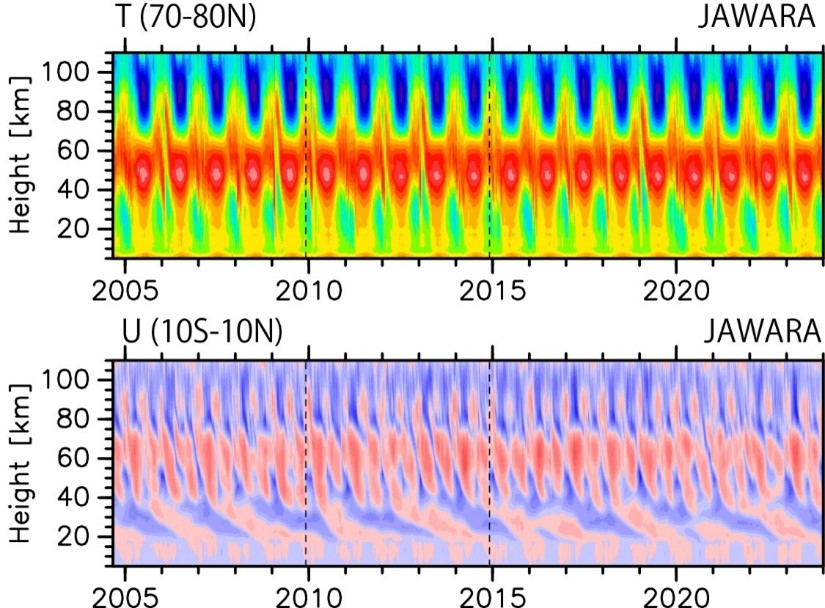 1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学  1702地球物理及び地球化学
1702地球物理及び地球化学