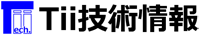2025-02-25 静岡大学
静岡大学の竹内 純 准教授は、同大学の中村 彰彦 教授と明治大学の瀬戸 義哉 准教授と共同で、高温ストレス下での植物の発芽制御に関わるKAI2(KARRIKIN INSENSITIVE 2)注1)というタンパク質がどのような分子構造を持つ物質(リガンド)と結びつくことで生理応答が起こるのかを明らかにしました。
地球温暖化により、高温ストレスが原因で植物の発芽が妨げられることは、農作物の収穫量に大きな影響を与える深刻な問題です。最近の研究で、植物ホルモンであるストリゴラクトン 注2)の受容体(D14)の仲間であるKAI2が、高温環境での植物の休眠や発芽の調節に関与していることが報告されています。しかし、KAI2と結合する植物内生リガンド 注3)(KL)はまだ同定されておらず、そのメカニズムもよく分かっていません。
そこで本研究では、KAI2のリガンドがどのような分子構造を持っている必要があるのか、またKAI2がどのように活性化されるのかを解明しました。具体的には、KAI2と結合することが知られているdMGer 注4)という物質(KAI2アゴニスト 注5))の構造を改変して、KAI2と結合するが、KAI2によって加水分解されないような構造としたdMGerアナログ(類似物質)を設計しました。このアナログを使って、KAI2との結合活性や植物への効果を詳しく調べました。解析の結果、KAI2を活性化するためには、リガンドがKAI2と結合するだけでは不十分であり、リガンドのブテノライド環 注6)が加水分解され、その後KAI2の触媒残基 注7)と共有結合を形成することが重要であることが分かりました(図1)。
本成果は、10年以上発見されていなかったKLの構造的特徴に関する新しい知見を提供し、KLの探索研究を大きく前進させるものと期待されます。また、植物の高温発芽阻害の解決にKAI2経路を利用した新規農薬ターゲットを創り出せる可能性もあります。この研究成果は、2025年2月20日に国際学術誌「Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)」のオンライン版で公開されました。
本成果は、以下の事業・研究領域・研究課題によって得られました。
■ 戦略的創造研究推進事業ACT-X
・研究領域:「環境とバイオテクノロジー」(研究総括:野村 暢彦 筑波大学 生命環境系 教授)
・研究課題名:「高温ストレスによる発芽阻害メカニズムの解明」(課題番号:JPMJAX21BE)
・研究代表者:(竹内 純 静岡大学 准教授)
・研究期間:令和3年10月~令和6年3月
 図1 研究概要
図1 研究概要
KAIリガンドの構造を一部改変した化合物を合成し、それらの活性を詳細に解析することで、KAI2の活性化には①リガンドが加水分解され、②その後KAI2触媒残基と共有結合を形成することが重要であると明らかにしました
【論文情報】
タイトル:Structural requirements of KAI2 ligands for activation of signal transduction
著者:Rito Kushihara, Akihiko Nakamura, Katsuki Takegami, Yoshiya Seto, Yusuke Kato, Hideo Dohra, Toshiyuki Ohnishi, Yasushi Todoroki, and Jun Takeuchi*
掲載誌名:Proceedings of the National Academy of Sciences
DOI:10.1073/pnas.2414779122
【用語説明】
注1)KARRIKIN INSENSITIVE 2(KAI2)
山火事などで植物が燃焼した際の煙に含まれる発芽刺激物質(karrikin)と結合するタンパク質として2012年に同定された。
しかし、未だ植物内生リガンド(KAI2 ligand, KL)が同定されていないオーファン受容体(オーファンとは孤児の意。特異的に結合するリガンドが同定されていない受容体)。
注2)ストリゴラクトン(SL)
地上部において枝分かれ・分げつを抑制する植物ホルモンである一方、根圏においては共生・寄生の化学シグナルとして作用する生理活性物質。
ABAと同様に、カロテノイドの酸化開裂によって生合成される。
注3)植物内生リガンド
植物が生合成し、特定のタンパク質(受容体)と特異的に結合して生理活性を誘導する分子。
KAI2に関しては、外因性のリガンドとしてkarrikinや人工SLが報告されているが、内生リガンド(KAI2 ligand, KL)は未だ発見されていない。
注4)dMGer
2023年に明治大学の瀬戸らによって開発されたKAI2選択的アゴニスト。
KAI2は活性化する一方で、そのパラログであるストリゴラクトン受容体に対してはアゴニスト活性を示さない化合物。
注5)アゴニスト
受容体に特異的に結合し、受容体の機能を活性化することで細胞内情報伝達系を作動させる物質。
KAI2にアゴニストが結合すると、KAI2の構造が不安定化して、パートナータンパク質との相互作用を介してシグナル伝達が誘導される。
注6)ブテノライド
ラクトンの一つで、炭素数4の複素環式化合物。
最も単純なブテノライドは2-フラノンであり、天然に多く存在し、ストリゴラクトンも分子内にこの構造を含んでいる。
注7)触媒残基
タンパク質(酵素)が反応を触媒する際に必須となるアミノ酸残基。
基質への求核攻撃を行うセリン(Ser)と、セリンの求核性を高める役割を果たすヒスチジン(His)とアスパラギン酸(Asp)の三つのアミノ酸残基がこれに相当する。
KAI2においては、リガンドへの求核反応によってリガンドと触媒残基が共有結合を形成する。
【詳細はこちら:プレスリリース】
高温ストレス下で植物の発芽を調節できるタンパク質の活性化機構を解明 ~植物の高温発芽阻害の解決に向けた新たな知見を提供~
お問い合わせ先:
<研究に関すること>
竹内 純(タケウチ ジュン)
静岡大学 准教授
瀬戸 義哉(セト ヨシヤ)
明治大学 准教授
<JST事業に関すること>
原田 千夏子(ハラダ チカコ)
科学技術振興機構 戦略研究推進部 先進融合研究グループ
<報道担当>
静岡大学 広報・基金課
明治大学 経営企画部広報課
科学技術振興機構 広報課